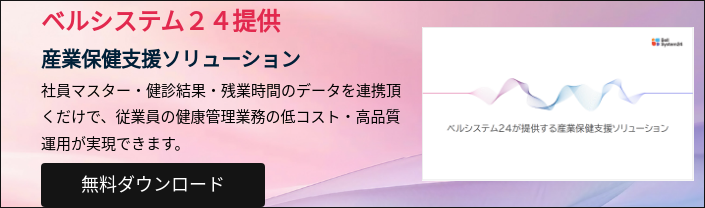知っておきたい労基対策!中小企業における従業員の「健康管理」とは
- 2025.01.10
- 健康維持・増進
- ウェルネスの空 編集部
従業員の健康管理は本人が健やかに暮らせるだけではなく、人材不足や高齢化が進む今、雇用する側のリスクヘッジや持続的な事業活動に影響するものです。この記事では、労働基準監督署によって行われる調査の内容や企業が守るべき義務、従業員の健康管理が企業価値の向上につながる理由やそれを叶えるサービスについて詳しく解説します。
.png?width=637&height=358&name=wellness%E6%A7%98%7C%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0%E7%94%BB%E5%83%8F%20(13).png)
労基の調査が入るきっかけとは?
労働基準監督署(労基)は厚生労働省の第一線機関であり、全国に321署存在します。その主な役割は次の3つです。
・申告、相談の受付
・監督指導
・司法警察事務
労基による調査は、臨検監督とも呼ばれます。頻繁に行われるわけではありませんが、実際に調査が入ることになったケースも存在します。この調査が実施されるきっかけは、主に次の3つです。
・定期申告:労働基準監督署の年度計画に基づいた調査
・申告監督:賃金未払いや解雇など、従業員や退職者からの依頼があり実施される調査
・災害時監督:労働災害が一定の規模以上だった場合に実施される調査
また、前回の結果が是正されているかどうかの確認調査である「再監督」が行われる場合もあります。
労基から指摘されやすいポイント
調査において企業が労基から指摘されやすいポイントは、以下の通りです。
・労働時間管理の不備
・残業代の未払いや計算ミス
・36協定の未締結や不適切な運用
・就業規則の未作成や内容の不備
・年次有給休暇の取得状況や管理の不適切さ
・労働条件の明示不足
・賃金台帳や労働者名簿などの法定帳簿の不備
・健康診断の未実施や結果報告の不備
・安全衛生管理体制の不備(安全管理者や衛生管理者の未選任など)
・最低賃金法違反
・労働安全衛生法に基づく措置の不履行
調査でこれらの点について指摘を受けないためには、日頃から法律に則って適切な管理・対応をしておくことが重要です。
企業が社員の健康管理をするのは必須
「労基から指摘を受けやすいポイント」を怠ることは、すなわち、企業が健康診断を適切に実施していなかったり、職場環境や勤務スタイルに応じた健康への配慮が不足していたりすることを意味します。これは労基から何らかの指摘や指導を受ける可能性があるだけではなく、健康を損なうことで社員が仕事を続けられなくなったり、重大な事故につながってしまったりする可能性を孕んでいるのです。
企業に課される「安全配慮義務」とは?
労働契約法第五条には「使用者は労働者に対して、労働契約に伴い、労働者の生命、身体等の安全に配慮しなければならない」ことが記載されています。これが「安全配慮義務」です。安全配慮義務には、大きく「職場環境配慮義務」と「健康配慮義務」の2つに分かれます。
職場環境配慮義務では、働きやすい環境になるように物理的な面(室温など)で環境を整えることに加えて労働時間の管理、業務に応じた適切な人員配置、労働者の病歴や体調などを考慮した適切な業務配置などに対策を講じることが求められます。また、パワーハラスメント防止やコミュニケーションの機会創出といった面にも配慮が要ります。
そして、健康配慮義務は社員の健康管理全般への取り組みを指します。具体的には、定期的な健康診断や診断結果に応じた受診勧奨、メンタルヘルス対策など身の健康状態の把握と管理に努めるための施策などです。
企業は法的義務を果たすため、これら従業員の健康管理に積極的に取り組む必要があります。
参照元:労働契約法第五条|e-Gov検索
従業員が50人以上の企業に課される5つの義務とは?
雇用する従業員が50人以上の企業には、さらに5つの主要な義務が課されます。
・産業医の選任義務
産業医とは、企業や施設を勤務先とする医師のことです。該当する企業は産業医を選任し、労働者の健康管理などを行います。産業医は労働者の健康管理や職場環境の改善、健康教育などを担当します。
・衛生管理者の選任義務
衛生管理者は、第一種衛生管理者免許などの資格を有する担当者で、該当企業は選任する必要があります。衛生管理者は労働者の健康障害を防止するための措置や衛生教育などを行います。
・衛生委員会の設置義務
衛生委員会は、労働者の健康に関する重要事項について調査・審議するための組織です。労働安全衛生法第十八条に基づいて設置されます。該当する企業は衛生委員会を設置し、毎月1回以上開催する必要があります。
・ストレスチェックの実施義務
ストレスチェックは従業員のストレス状態を検査する制度です。年1回、このストレスチェックを実施しなければなりません。
・健康診断結果報告書の提出義務
該当する企業では、定期健康診断の結果を所轄の労働基準監督署長に報告する義務があります。
これらは労働安全衛生法に基づいて定められており、従業員の健康管理と職場の安全衛生を確保するために重要です。単なる法令遵守としてではなく、従業員の健康と生産性向上につながる健康経営の一環として積極的に取り組むことが望まれています。
従業員の健康管理は生産性や企業価値の向上にも寄与する
従業員の健康管理は、法的義務であるだけではなく持続的かつ発展的な事業活動を行う上で必要な取り組みです。日本全体で進む人材不足や従業員の平均年齢の高まりを鑑みて、企業に身を置く誰もが健康に働き続けるための健康経営といった観点からも重要視されているのです。したがって、適切な健康管理を行う企業には以下のようなさまざまなメリットが享受されると考えられます。
・生産性の向上
健康な従業員のほうが高い生産性を発揮することは容易に想像できます。
・業績向上
顧客に高品質の商品やサービスを提供できれば、業績の向上も期待できます。
・企業価値の向上
健康経営への取り組みは、企業価値を高めることにつながります。ブランディングにも効果的です。
・人材の定着と採用
健康管理に注力することは、従業員の定着率向上にもつながります。働きやすい会社であるという評価は、優秀な人材誘致にもプラスの影響を与えます。
中小企業の健康管理をまとめて解決
こうした社会情勢の流れを受けて開発されたのが産業保健支援ソリューションサービス「まとめて健康管理」です。人事・労務部門のご担当者に代わって、健康管理にまつわる業務を一括代行いたします。
このサービスに含まれるのは、以下の3つです。
・健康管理業務の運用支援
・クラウド上で従業員の健康状態を可視化・一元化
・経験豊富な担当者によるサポート
「まとめて健康管理」サービスの導入によって、効率的かつ確実に労働安全衛生法に対応できるようになります。さらに、産業保健や健康経営に関する施策立案・実行においては、労働安全衛生法対応経験者や医療有資格者といったプロのサポートを受けられます。
参考ページ:産業保健支援ソリューション
まとめ
労働基準監督署による調査のきっかけは主に定期申告、申告監督、災害時監督の3つです。調査では労働時間管理や残業代支払い、36協定、就業規則などが重点的に確認されます。こうした調査は労働契約法第五条に記載された安全配慮義務に基づいて行われます。
また、従業員の健康管理は、生産性向上や業績向上、企業価値向上、人材定着・採用にも寄与する重要な経営戦略です。そのため、中小企業でも健康経営に積極的に取り組む事例が増えています。
「まとめて健康管理」を導入すれば、健康管理業務の一括代行や低コスト運用、法令遵守、業務効率化、リスク管理、コンプライアンス強化、データ活用などが可能です。ぜひご検討ください。
この著者の最新の記事
-

- 2025.02.21
- 健康維持・増進
健康づくりのきっかけになる「特定保健指導」とは?必...
-

- 2025.02.19
- 健康維持・増進
ウェルネスにおけるサプリメントを解説 従業員の健康...
-

- 2025.02.14
- 診断・治療
医薬品の流通管理|現状や課題、解決方法について解説
-

- 2025.02.10
- 診断・治療
くすり相談窓口:医薬品の適正使用を支える重要な存在
.png?width=360&height=230&name=wellness%E6%A7%98%7C%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0%E7%94%BB%E5%83%8F%20(13).png)
この記事が気に入ったら
いいねしよう!